話題レポート

《Eimei「みちしるべ」》
(5月7日から5月10日の週)
連休中の動向。
↓
先々週末26日金曜のNY株式市場は上昇。
S&P500とNASDAQは終値ベースで過去最高値を更新。
週間ではNYダウが0.06%下落、S&P500は1.2%上昇、NASDQは1.86%上昇。
第1四半期の実質GDP速報値が年率換算で前期比3.2%増と前期の2.2%増から加速。
市場予想の2.0%増を大幅に上回ったことを好感。
10連休前のNYダウ26543ドル。
NASDAQは8146ポイント。
S&P500は2939ポイント。
ダウ輸送株指数10881ポイント。
SOX指数1547ポイント。
シカゴ225先物22335円。
先週月曜29日のNY株式市場は小幅高。
NASDAQやS&P500が最高値を更新した。
個人消費支出は前月比0.9%増と9年半ぶりの大幅な伸びを記録。
物価は対照的に約1年ぶりの小幅な伸びにとどまるなど落ち着いた動きとなったことを好感。
3市場の売買高は58.1億株と低調。
30日火曜のNY株式市場はマチマチの動き。
NYダウとS&P500は3日続伸。
S&P500は終値ベースの史上最高値を更新した。
一方NASDAQは4日ぶりの反落。
アルファベットの低調な決算を嫌気した格好だ。
アップルの四半期決算は減収減益ながら1株利益と売上高が市場予想を上回って着地。
終値は1.9%安だったが決算発表を受け、引け後に4%超上昇。
自社株買いと増配も好感した格好。
3市場の売買高は72.2億株と増加。
月間ベースでNYダウは2.6%高、4カ月続伸(累計14.0%上昇)。
NASDAQは4.9%高、2カ月ぶり上昇。
S&P500は3.9%高、4カ月続伸(同17.5%上昇)。
中国の製造業購買担当者景気指数(PMI)は前月比0.4ポイント低下し50.1。
節目となる50は2カ月連続で上回ったが2カ月ぶりの悪化。
ユーロ圏GDP速報値は前期比0.4%増で前年比1.2%増。
市場予想(前期比0.3%増、前年比1.1%増)を上回った。
5月1日水曜のNY株式市場は下落。
アップルがけん引して相場はおおむねプラス圏で推移。
S&P500は一時最高値を更新する場面もあった。
ただFOMC通過後にパウエル議長が「今年のインフレ低下は一時的な要因によるものである可能性がある」とコメント。
市場で広がっていた利下げ観測は後退。
年末の利下げ確率が低下したことを嫌気したとの解釈。I
SM製造業景気指数は52.8と3月の55.3から低下。
予想の55を下回り2016年10月以来2年半ぶりの低水準を記録した。
ADP雇用レポートで民間部門雇用者数は27万5000人増。
市場予想の18万人増を大きく上回り2018年7月以来の高い伸びとなった。
3市場の売買高は74.4億株。
5月2日木曜のNY株式市場は続落。
供給過剰懸念による原油安よるエネルギーセクターの下落が効いた格好。
「S&P500が過去最高値を付けたことから投資家は様子見」という見方もある。
年末の利下げ確率は49%で1日時点の61%から低下した。
非農業部門労働生産性は年率で前期比3.6%上昇。
2014年第3四半期以来の大幅な伸びとなった。
3月の製造業新規受注は前月比1.9%増と18年8月以来の大幅増。
ダウ輸送株指数とSOX指数は反発。
VIX指数は14.42。
先週末4日のNY株式市場は反発。
NYダウは200ドル近い上昇。
NASDAQは1.6%上昇し終値ベースの過去最高値を更新した。
背景は4月の雇用統計。
非農業部門の雇用者数が26万3000人増と市場予想の18万5000人増を大幅に上回って着地。
失業率は3.6%で1969年12月以来約49年ぶりの水準にまで改善した。
一方、ISM非製造業総合指数は前月比0.6 ポイント低下の55.5。
17年8月以来の低水準だった。
3市場の売買高は64.7億株と低下。
10年債利回りは2.53%。
12月の利下げ確率は約47%と低下。
ドル円は111円台前半。
VIX指数は12.87。
週末のNYダウは26504ドル(前週末26543ドル)。
NASDAQは8164ポイント(同8146ポイント)。
S&P500は2945ポイント(同2939ポイント)。
ダウ輸送株指数10958ポイント(同10881ポイント)。
SOX指数1570ポイント(同1547ポイント)。
シカゴ225先物22475円(同22335円)。
4月19日時点の信用買残は652億円減の2兆1190億円。
2週連続の減少。
同信用売残は431億円増の9771億円。
3週連続の増加。
昨年の最大値9月下旬の1兆673億円に近づいてきた。
2015年のピークは8683億円。
そう考えると結構売り残は高水準だ。
「信用売り残のピークは急落のシグナル」という嫌な経験則は忘れたいところ。
4月19日時点の裁定買い残は464億円減の1兆807億円。3週連続の減少。
同裁定売り残は485億円減の6529億円。3週連続の減少。
SQまたぎでの減少だろうが、裁定取引はやる気なしという水準だ。
結局、NY動向を受けて「月曜高、木曜安」のリズムは変わっていなかったというのが先週末までの9連休。
しかし・・・。
余計だったのが、というかタイミングを図ったように東京市場をカナリアにしたのは週末日曜のトランプ大統領のツイート。
「2000億ドル相当の中国製品に対する関税を10日から現在の10%から25%に引き上げる。
中国との通商協議は継続しているが遅すぎる。
中国側は再交渉しようとしている。ノーだ」。
現在関税を課していない3250億ドル相当の中国製品についても、近く25%の関税を発動する考えだという。
関税引き上げの表明は大きな方向転換。
「貿易戦争が激化すれば金融市場に打撃が及ぶのはほぼ確実」という見方が台頭した。
日本では「こどもの日」の大人げないタイミングでの卑怯なツイート。
「ちゃぶ台返し」で10連休の終わりを台無しにしたような格好だ。
月曜の上海株は一時6%の下落。
人為的な株安には人為的な株高で対抗するのが現代株式市場の鉄則だろう。
「人災には天恵、潤色で対抗」だ。
日経平均想定レンジ
下限21870円(4月SQ値)~上限23373円(10月10日マド明け水準)
「市場を動かす感情は一体何なのか」をCNNマネーが見える化したのが「恐怖と欲望指数」だ。
投資家は恐怖と欲望という2つの感情によって動かされる。
投資家が強い恐怖を感じると、株式を投げ売りして適正価格よりも過度に下回る。
反対に投資家が欲張りになると、株価が高値でもどんどん買い上げて、適正価格よりも過度に上昇する。
それを目で見てすぐわかるようにしてある。
4月23日段階で「75ポイント」は「極端な欲張り状態」。
理由は・・・。
プットの売買が少なく多くの投資家は「強気」。
安全資産の米国債から株式への資金シフトが継続。
米国債に対する米株のパフォーマンスは過去2年の最高水準。
因みに1週間前は70ポイント。
1ヶ月前は59ポイント。
1年前は40ポイントだった。
リーマンショック後の2008年9月17日は「12」。
「ビビリと欲張り指数」と言っても良いかも知れない。
「他人が貪欲になっている時は臆病に、他人が臆病になっている時は貪欲に」
(ウォーレン・バフェット)
とはいえ・・・。
「注意しましょう、警戒しましょう」という市場関係者の免罪符通りに持ち株を全部売れるものだろうか。
それが出来ていたのなら、塩漬け株などないはず。
それでも株の倉庫があるということは「警戒しましょう」なんで呪文に効き目はないということ。
建前と本音は違うのは当然。
しかし「警戒しましょう」と言った人物が、強まってくると「思ったとおりに上昇です」。
というのが市場。
「警戒しましょう」は親切ではなく自分の免罪符。
下がった時に「申し上げたとおり」の常套句。
上がったときは「忘れたフリ」。
右顧左眄して儲かることは少ない。
逆にヘッジするくらいなら売っておけば良いとも言えるが・・・。
物事を複雑にしないほうが良いだろう。
S&P500のシャープレシオは昨年9月以来のプラス圏。
シャープレシオとは・・・。
リスク(標準偏差)1単位当たりの超過リターン(リスクゼロでも得られるリターンを上回った超過収益)を測るもの。
この数値が高いほどリスクを取ったことによって得られた超過リターンが高いこと(効率よく収益が得られたこと)を意味する。
「10連休中にNY株が新高値を更新すれば連休明けの日本株への外国人買い期待」とのレポートもある。
世界の大型株で運用するファンドの日本株組入比率は3月時点で7.16%。
2014年4月以来約5年ぶりの低水準だ。
日経朝刊ではNYダウと日経平均の比率の「NDレシオ」を持ち出してきた。
3月末の値が0.82倍で13年1月以来の低水準。
2002年以降は0.8~1.5倍前後のレンジが平均だ。
「閑散にウリなし」という格言もある。
「信用買い、10年ぶり低水準」という指摘がある。
東証1部の時価総額に対する信用買残の比率は4月5日時点で0.33%。
19日時点では0.35%。
2009年4月10日の0.353%以来の水準。
その後2013年6月には0.82%まで上昇したのが歴史。
「買い残の少ない銘柄は売り圧力が少ない」というのがセオリー。
だとするならば売り残は高水準、買い残はスカスカ、逆日歩オンパレードというのは悪くない。
平成の時代に染み付いた「株は上がらない」という心理。
これを掃除するのにいい機会が訪れたのかも知れない。
因みに・・・。
貸株超過数(貸株が融資残高を上回り過去25日の売1日あたり平均売買高で割った数値)。
これが1日あたりの売買高に匹敵するほど貸株が積み上がっている銘柄群。
キーエンス(6861)、ファーストリテ(9983)、SMC(6273)、
コーセー(4922)、ディスコ(6146)、ファナック(6954)、
大東建(1878)、シマノ(7309)、東エレ(8035)、
日電産(6594)、OLC(4661)、小林製薬(4967)、
ZOZO(3092)、資生堂(4911)、明治(2269)、
GMOPG(3769)、スズケン(9987)、京王(9008)、ABCマート(2670)。
孫さんが損をした話。
ウオールストートジャーナルの報道。
ソフトバンクの孫正義氏は仮想通貨ビットコインへの投資で約1.3億ドルの損をしたという。
145億円など資産2兆円を超える人には大したことでもなかろう。
しかし不損神話は崩壊した。
「孫さんも損をする」と解釈するか
あるいは「仮想通貨は孫さんでも思い通りにならない」と解釈するか。
できれば後者の方と考えたい。
しかも高値の絶頂の2017年に投資し急落した18年に売却。
素人っぽい動きに見えてならない。
実像が虚像に変わらなければ良いが・・・。
(兜町カタリスト 櫻井英明)
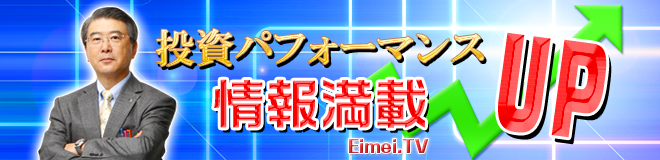








 メルマガ
メルマガ

