話題レポート

《Eimei「みちしるべ」》
《Eimei「みちしるべ」》(7月14日→7月18日の週)
7月4日時点のQuick調査の信用評価損率は▲8.44%(前週▲7.44%)。
7月4日時点の信用売り残は349億円減の8417億円。
2週連続で減少。
同信用買い残は1020億円増の3兆9411億円。
2週ぶりに増加。
2週連続で3兆円台。
昨年6月21日時点は4兆9117億円。
信用倍率は4.68倍(前週4.38倍)。
4月4日が9.63倍、昨年8月9日が7.48倍、8月2日が8.72倍。
7月4日時点の裁定売り残は184億円増の1201億円。
2週ぶりに増加。
当限は184億円増、翌限以降はゼロ。
裁定買い残は1005億円減の1兆4909億円。
3週連続で減少。
当限は1005億円減、翌限以降はゼロ。
7月第1週(6月30日→7月4日)の需給動向
海外投資家は現物5775億円買い越し(14週連続で買い越し)。
4月第1週以来のこの間の累計買越し額は4.9兆円。
23年6月の12週連続以来2年ぶりの長期買い越し。
過去最高は13年3月までの18週連続。
「10週以上の連続買い越しは大相場の起点」という声もある。
12年11月から18週連続で買い越したときの当初13週間の買越額は3兆4909億円。
今回は当時よりも買越額が大きい。
因みに18週では海外勢が合計で5兆6692億円を買い越していた。
先物2992億円買い越し(5週連続で買い越し)。
合計2782億円買い越し(12週連続で買い売り越し)。
個人は現物980億円売り越し(4週連続で売り越し)。
信用544億円買い越し(5週ぶりに買い越し)。
合計436億円売り越し(4週連続で売り越し)。
信託銀行は現物881億円買い越し(11週ぶりに買い越し)。
先物2216億円買い越し(2週ぶりに売り越し)。
合計1344億円売り越し(2週ぶりに売り越し)。
7月第1週(6月30日→7月4日)の投資部門別売買代金。
個人が現物3094億円売り越し(前週4305億円売り越し)。
信用2490億円買い越し(前週1611億円売り越し)。
海外投資家が5456億円買い越し(前週3398億円買い越し)。
自己売買が6728億円売り越し(前週530億円買い越し)。
信託銀行が848億円買い越し(前週473億円売り越し)。
事業法人が2454億円買い越し(前週420億円買い越し)。
14週連続で買い越し。
今年の曜日別勝敗(7月12日まで)
↓
月曜14勝11敗
火曜16勝8敗
水曜15勝12敗
木曜15勝11敗
金曜11勝16敗
★2024年度株式分布状況調査の調査結果について
1. 個人株主数は、前年度比914万人増加して8,359万人となった。
2.投資部門別株式保有金額は、全ての区分において前年度比マイナスとなり、特に事業法人等
が大幅に減少する結果となった。
3.外国法人等の株式保有比率は、前年度比プラス0.6ポイントの32.4%となり、調査開
始以来、過去最高となった。
4.個人・その他の株式保有比率は、前年度比プラス0.4ポイントの17.3%となった。
5.信託銀行の株式保有比率は、前年度比プラス0.3ポイントの22.4%となった。また、
投資信託の株式保有比率も前年度比プラス0.3ポイントの10.7%となり、調査開始以
来、過去最高となった。
6.事業法人等の株式保有比率は前年度比マイナス0.6ポイントの18.7%となり、調査開
始以来、過去最低となった。
↓
https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/examination/um3qrc000001nwjv-att/j-bunpu2024.pdf
★市場区分の見直しに関するフォローアップ(7月9日開催)
特にグロース市場で新基準の適用開始は原則2030年とするものの、
企業が追加期間を設けて新基準への適合を目指す計画を投資家
に開示する場合、その計画期間はグロース市場への上場を例外的に可能とする(2025年9月を目途に制度要綱を公表)
↓
資料1 今後の取組みについて
資料2 「資本コストや株価を意識した経営」に関する今後の取組みについて
資料3 IR体制・IR活動に関する投資者の声
資料4 グロース市場における今後の対応
資料5 スタンダード市場の今後の方向性
資料6 経過措置適用会社の状況
↓
https://www.jpx.co.jp/equities/follow-up/index.html
★日経平均想定レンジ
下限39092円(25日線水準)―上限が41365円(ボリンジャーのプラス3σ水準)
日経朝刊では「企業の配当総額20兆円。家計に3.5兆円」の見出し。
2026年3月期の配当総額は19.99兆円と前期比3%増。
5年連続で過去最高の見通しだ。
今期増配見通しは910社で全体の約4割に及ぶ。
減益でも増配の企業は250社。
プライム上場3月決算企業の手元資金は約112兆円。
資本効率を追求されると、バブル崩壊以降虎の子だった現金も炙り出される格好だ。
当然株価は業績と配当を重視する。
しかし、それだけだろうか。
「定量」は欧米、特にアメリカで求められる。
それは共通文化でなく、数字はだれでも簡単に読めるから。
曖昧模糊とした「定性」はあまり好まれない。
なぜなら、理解不能に陥るから。
でもIRに最終的に求められるのは「成長ストーリー」だと思っている。
決して定量的には表現できないからこそ、そこに投資家は惹かれるのではなかろうか。
元旦の日経朝刊1面の見出しは「逆転の世界。備えよ日本」。だった。
サブタイトルは「強まる自国第一 貿易ルール瓦解」。
半年前に経済紙が予告していることは起こっているのが現実。
備えてはいなかったかもしれないが、順応してきた格好だ。
起きているのは天災ではなく、人災。
所詮、地球と違って人間の行為には限界がある。
美味しい町中華のお店ではよく首や背中が曲がったご主人に遭遇する。
「長い間重い鍋を振ってきたから」というのが理由とされる。
しかし、これはすごいことだといつも思う。
何十年も同じ作業をしながら、料理の味を昇華させてきた結果に他ならない。
何十年も同じ作業をするという意味では株式市場だって一緒だが決してその結果が料理の味に反映する訳でない。
せいぜいペンだこが残っているか、指が腱鞘炎になるくらい。
近視も乱視も老眼も進むが、それでも至高の味にはまだ遠い。
経済産業省のHPの「国内投資マップ」
↓
https://www.meti.go.jp/press/2025/07/20250708002/20250708002-a.pdf
夢にヘビが登場した。
でも黄金でなくフツーのアオダイショウやシマヘビっぽい群れ。
1匹の死んでいるネズミに群がっていた。
もっともヘビたちの何匹かはなぜか微笑んでいた。
死んだフリしている小型株の復活の暗示だろうか。
(兜町カタリスト 櫻井英明)
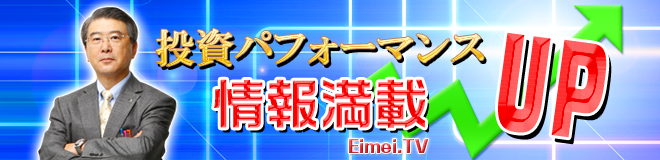








 メルマガ
メルマガ

