Eimei みちしるべ 2015年08月31日
 《Eimei「みちしるべ」》
《Eimei「みちしるべ」》(8月31日から9月4日の週)
25日まで6日間で2813円値下がり。
28日までの3日間で1329円円上昇。
一応「嵐」は去った。
しかし逆説的アノマリーとして興味深いのは週刊誌の見出し。
東洋経済は「世界同時株安、その先の悪夢」。
ダイヤモンドは「世界株暴落の震源地、中国経済の先行きが15分でわかる」。
エコノミストが一番おどろおどろしく「中国ショック、株・原油暴落」。
マスコミや書店が暴落論一色の時は株を買い向かうのが、セオリーでもあろうか。
この間活躍していたのがレバレッジ型のETF。
値動きが通常の株価指数より大きい「レバレッジ型」のETFに個人投資家の資金が集中した。
特に日経レバ(157)は週末28日に新規設定一時停止。
28日取引終了後上限を1兆円に拡大した。
個人投資家から500億円の資金流入があった場合、日経レバは新規設定。
日経平均先物の約1000億円の買い需要が生まれるというから怪物である。
夏の終わりの恒例行事はジャクソンホール。
米ワイオミング州でのカンザスシティー連銀主催の経済シンポジウム。
フィッシャーFRB副議長は講演で9月利上げの言質を与えずとの報道。
中国経済の情勢などを見極める姿勢に徹したという。
週末の雇用統計も踏まえて利上げを最終判断するという。
そしてシンポジウムでは「中国発の市場の動揺が世界経済に与える打撃は限定的」。
市場の乱高下が収まれば利上げの環境が整うという解釈となっている。
まあ、大きなポジサプライズはなく通過ということなのだろう。
一方でトムソン・ロイターの調査。
米S&P500採用企業の2015年第2四半期決算は、前年同期比で1.4%の増益見通し。
利益がアナリスト予想を上回った企業は70%。長期平均の63%、過去4四半期の平均69%を上回った。
売上高がアナリスト予想を上回った企業の比率は48%。
逆に長期平均の60%、過去4四半期の平均56%をともに下回っている。
第3・四半期の1株利益について、悪化もしくは市場見通しを下回ると予測している企業は84社。
改善もしくは市場見通しを上回ると予測した企業は25社。
悪化を改善で割ったネガティブ/ポジティブレシオ(84/25社)は3.4。
500社の今後4四半期(15年第3四半期~16年第2四半期)の予想株価収益率(PER)は16.1倍。
意外と悪くない。
日経平均想定レンジ
下限19031円(200日線)~上限19894円(7月SQ値)
3日新甫でスタートした8月。
4月上昇8月下落のアノマリーは残念ながら今年は外れなかった。
だったら7月上昇10月上昇のアノマリーも実現して欲しいもの。
改めて振り返ってみると\\\/
1月月足陽線基準は17408円(1月5日終値)
昨年比プラス基準は17450円(12月30日終値)
6月月足陽線基準は20569円(6月1日終値)
7月月足陽線基準は20329円(7月1日終値)
8月月足陽線基準は20548円(8月3日終値)
12月SQ値は17281円。
3月SQ値は19225円。
4月SQ値は20008円。
5月SQ値は19270円。
6月SQ値は20473円。
7月SQ値は19894円。
8月SQ値は20540円。
3月月中平均は19197円。
ある指摘は「最近の株価の下落は暴落は7年に1度の暴落。
今年はその暴落の年で7年前は2008年のリーマンショック。
その前は2001年の9.11多発テロ。
1994年 アメリカ国債暴落
1987年 ブラックマンデー
1980年 ハードリセッション
1973年 オイルショック」。
こういう見方もしたくなってくる。
ただ基本は金融相場から業績相場への移行途中の中間反落と考えたいところ。
38915円に至った昭和バブルのスタートは1982年。
しかし途中1887年にブラックマンデーに見舞われた。
これが中間反落となり、その後高値を示現したのが歴史。
歴史は繰り返すと考えたいところ。
(兜町カタリスト 櫻井英明)
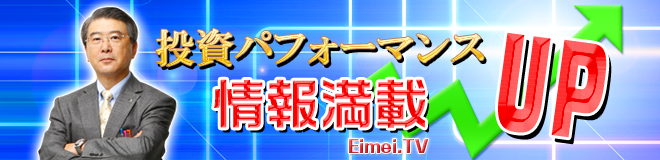








 メルマガ
メルマガ

