英明コラム 1月第5週 マーケットストラテジーメモ
 |
「英明コラム 1月第5週 マーケットストラテジーメモ」 |
《マーケットストラテジーメモ一覧へ》

《マーケットストラテジーメモ》01月 第5週
27日(月):
週末のNY株式市場で主要3指数は揃って5日ぶりに反落。ハイテク関連銘柄が軟調。エヌビディアが3.1%安。マイクロソフトが0.6%安。テスラが1.4%安。ただ週間では主要株価3指数は2週連続で上昇。
S&P500が1.74%高、ナスダック総合が1.65%高、NYダウが2.15%高。
日経平均株価は366円安の39565円と続落。日経平均は一時300円高となったが、全体に買いの勢いは続かなかった。アドテストや東エレクといった値がさの半導体関連株が下落。中国企業が開発した生成AIに対する警戒も高まり下落幅は一時400円を超えた。TOPIXは反発。東証プライムの売買代金は4兆4651億円。ファストリ、富士フイルムが上昇。SBG、ニトリが下落。
28日(火):
週明けのNY株式市場で主要3指数はマチマチの展開。大手ハイテク企業の株価が軒並み大幅安となった。S&P500株価指数はウエート上位銘柄の下げを受け1.45%安と大幅続落。ただS&P500構成銘柄の値上がり数は300超。S&P500が約1.5%下落する中、値上がり数が300超えた。これはS&P500の構成銘柄が500となった1957年以降初めて。フィラデルフィア半導体指数(SOX)は9.15%安。2020年3月以来の大幅な下落率。
日経平均株価は548円安の39016円と3日続落。米ハイテク株安を背景にアドテストや東エレクなどの半導体関連が前日に続き売られ、日経平均の下落幅は600円を超えた場面があった。フジクラや古河電などの電線株にも売りが優勢。一方、三菱UFJが連日で上場来高値を更新。銀行や不動産など割安(バリュー)株銘柄群には買いが活発だった。TOPIXは小幅に反落。東証プライムの売買代金は5兆474億円。ソニー、塩野義が上昇。SBG、ファーストリテが下落。
29日(水):
火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って上昇。エヌビディアなどAI関連銘柄を買い戻す動きとの解釈。ナスダック総合が2%高で上げを主導。前日に17%安となったエヌビディアは8.9%上昇。フィラデルフィア半導体指数(SOX)も1.1%高。
日経平均株価は397円高の39414円と4日ぶりに反発。前日の米株式市場で主要3指数がそろって上昇した流れで継続。買い戻しが優勢の展開。オランダの半導体製造装置ASMLホールディングの決算が好調との受け止めから15時過ぎにかけて上場幅を拡大した。東証プライムの売買代金は4兆5188億円。リクルート、日東電が上昇。塩野義、ニトリが下落。
30日(木):
水曜のNY株式市場で主要3指数は揃って反落。FOMCは金利据え置き=利下げなしで通過。引けにかけて下落幅を縮小した。エヌビディアが4.1%、マイクロソフトが1.1%下落。マイクロソフトは時間外取引で1.5%下落。FRBは年内に計約0.46%利下げを行うとの見方。年内に0.25%利下げを2回行うとの観測の後退を反映。
日経平均株価は99円高の3万9513円と続伸。前日の米ハイテク株の下落を受けて安く始まったが、アドテストなど値がさの半導体関連株が朝安後に持ち直し、日経平均の押し上げた。TOPIXは続伸。東証プライムの売買代金は4兆4964億円。三井物、住友電が上昇。ファナック、ダイキンが下落。
31日(金):
木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って反発。マイクロソフトの業績見通しが失望を誘う一方、テスラの強気のコメントが支援材料との解釈。トランプ大統領がメキシコとカナダからの輸入品に25%の関税を課すと改めて表明し一時軟調となったが持ち返した。テスラが2.9%高。第4四半期の利益が市場予想を上回ったIBMが13%高。同社として1999年以来の上昇率を記録した。 SOX指数は2.29%高。
日経平均株価は58円高の3万9572円と3日続伸。決算発表が本格化し、好業績銘柄への買いが日経平均を支えた。TOPIXは3日続伸。東証プライムの売買代金は4兆6090億円。東エレク、フジクラが上昇。TDK、テルモが下落。
(2)欧米動向
欧州株式が上昇を継続している。
ロンドンFTSE100種指数は8600ポイントの節目を超え、最高値を更新。
ECBが中銀預金金利の0.25%引き下げを決めたことも追い風。
しかしそれだけが理由ではなかろう。
独DAX指数も年初から上昇を継続し、過去最高値を更新している。
景気の実態とはかけ離れた印象の欧州株。
欧州の最大の悩みはロシアとウクライナの問題。
これが片付くという読みが先行しているならばよい傾向ではある。
(3)新興国動向
中国は春節期間。
今年、中国政府は春節期間に過去最多の約90億人の移動が見込まれると発表している。
2020年までは延べ30億人程度で推移していたとされる。
コロナ禍から抜けたと宣言した後の23年は47億人といわれていた
昨年からは一般道を走る自家用車の移動人数まで含めるようになり、昨年は数字上一気に84億人に膨れ上がった。
(兜町カタリスト 櫻井英明)
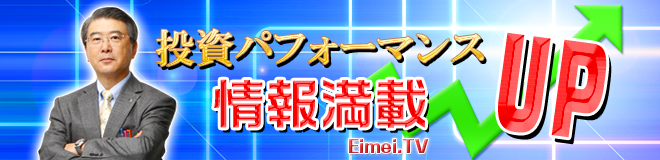








 メルマガ
メルマガ

