「暇な人」
 |
「暇な人」 |
7月のダウ平均は月間で6.7%高。
上昇率は20年11月以来の大きさだった。
ただ7月の株高について「弱気相場で一般的にみられるベアマーケットラリー(弱気相場の中での一時的上昇)にすぎない」。
そんな声が聞こえる。
米中対立の激化に対する警戒感は、利上げが米景気を冷やすとの見方とともに投資家のリスク回避を促したとの指摘。
相対的に安全な資産とされる米国債に資金が移り、米長期金利の指標となる10年物国債利回りは1日夜に2.51%まで低下。
一時は10年債の利回りが米財務省証券(TB)3カ月物の利回りを下回る「逆イールド」が発生した。
逆イールドは景気後退の予兆。
2年債と10年債では先月から発生している。
因みに・・・。
台湾を巡って軍事的危機が高まった1995ー1996年の第三次台湾海峡危機
日経平均株価が95年7月安値の1万4485円から96年2月高値2万1118円まで約45%上昇していた。
例年、8月の米株式市場は薄商いとなりやすい。
NYSEの月別売買高では、過去5年、10年平均いずれも8月の売買高が最も少ない。
多くの市場参加者が「夏休み」を取得する中、野村証券のクオンツリポートの指摘。
「投資判断を機械的に決定する商品投資顧問(CTA)にとっては夏休みはさほど影響せず」。
8月の日米株式市場はCTAのポジション変更による株価インパクトが大きくなる季節性がある。
「一部の市場関係者から、CTAによる株式買いを期待する声が聞こえている。
その根拠は、CTAによる株式の買戻し余地が大きいこと」という解釈だ。
野村証券によると、今後1か月間スポット価格が横ばいと仮定した場合、
CTAの自然体ポジションは1か月にわたり株式の買戻しが期待できると見込んでいる。
一方、2日の東京市場では「CTAによる株売り観測」が聞かれた。
JPモルガン証券のクオンツリポー。
「一段の日本株高をイメージするには、日経平均が2万7600円以上にとどまる環境。
そして主要投資家層に出遅れ警戒感が自然発生する必要がある」との見方。
「外圧的な円高が日経先物続伸の足枷となっている」との見方も。
CTAについて、ドル円が今年1月以降の平均買い越しコストである1ドル129円のトリガーレベルを割れることで追加で2000億円弱の円買い戻しが機械的に発生する可能性がある。
日経平均について、2万7600ー2万7700円を大きく割り込まない限り損失回避目的の持ち高清算に踏み切ることはない。
「世界の航空機を追跡しているフライトレーダー24」。
ペロシ氏が搭乗していたとみられる米軍機はクアラルンプールを2日午後に出発。
南シナ海を避けてフィリピンの東側を飛行して台湾に向かった」。
暇な人は結構多い。
(櫻井)。
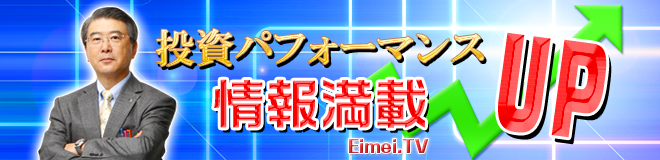








 メルマガ
メルマガ

