「久々にルービニ教授」
 |
「久々にルービニ教授」 |
「銃声が鳴ったら買え」というのは1815年ワーテルローの戦いでの有名な言葉だとの指摘は大和のレポート。
↓
過去の軍事衝突場面の日経平均を見ると攻撃開始時に株価は横ばい推移。
ほとんどの場合は12営業日後にほぼ変わらない水準を維持。
米軍の強大な軍事力が抑止力等となり結果的に短期間で収束しやすいためだろう。
この12営業日が経済トレンドへの影響を見定める期間。
その間で例外的に日経平均が下がってしまったのは1998年のイラク空爆。
当時は米国が予防的利下げ場面だった。
追加の利下げ期待がドルを押し下げ日経平均を押し下げる期間が11営業日程度あった。
ただし、追加の利下げ期待が米株や米国経済を支え様子見の12営業日以降の方向は上方だった。
そういえばワーテルローの戦いでのナポレオンの負けをいち早く知って英国債を買って大儲けしたのがロスチャイルド。
有名な話だ。
さらに昔を調べてみると・・・。
盧溝橋事件の時の東京の株価は大幅安。
これはおそらく事件の本日を見抜いて大幅安となったのは歴史的事実。
しかし真珠湾攻撃以降の株価は順調な上昇。
その後情報統制で正しい情報が伝わらず動意薄。
ガダルカナル撤退で急落しインパール作戦の前後に大幅安となった。
もっとも戦時金融公庫の無制限の買い支えもあり株価は終戦まで凍結状態だったという。
NYはどうだろう。
世界大恐慌以降軟調だったNYダウ。
390ドル(1929年)→42ドル(1932年)→187ドル(1937年)。
真珠湾攻撃の時が110ドル(1941年12月)→99ドル(1942年4月)→165ドル(1945年)。
開戦以降のNYダウは上昇していたのが歴史だ。
その後の朝鮮戦争の時のNYダウ。
200ドル(1950年)→399ドル(1954年)→500ドル超(1955年)。
この時はダウも東京も大きく上昇していたのが歴史。
今年の年初の日経平均。
●〇●で負け越し。
昨年は●○○だった。
ちなみに・・・。
1949年の東証再開以来最悪の大発会は2008年の616円安。
「戦後最悪の大発会」を大半が覚悟した。
確かに一時700円超の下落。
しかし後場には切り返して425円安。
戦後最悪は免れた。
この「覚悟」の先に今があるというのも事実だ。
「気の利いた化け物は引っ込む時分」という諺が妙に心に染みてくる。
「月日変われば気も変わる」だ。
「今日のあとに今日なし」の域の真逆だろう。
「下げ続ける相場」も「上げ続ける相場」もないのである。
昨年1月5日の日本一早いセミナーでの事前質問で多かったのは「空売り候補銘柄は?」。
これは典型的な反発サインだったのだろう。
もっとも、市場にあるのは「株は下げなきゃ上がれない」だった。
今年は「どの銘柄が一押し?」
だいぶ風景は違っている。
先日の日経スクランブルにも登場していたが最近静かなのは「恐慌博士ルービニ教授」。
話題になったのは「20年には経済危機」というコメント。
↓
米国が大きな財政赤字を容認し、中国が緩い財政・金融政策を追求。
欧州が回復基調を続けていることを考えれば、現在の世界的景気拡大は来年も続くだろう。
しかし2020年までには金融危機の土壌が出来上がり、その後世界的な景気後退がやってくるだろう。
「昨年までは経済危機は予想されないと話していたから、久しぶりに終末博士の面目躍如だ」。
これが昨年の解釈。
今年のスクランブルでは「3日に米国とイランの応酬は湾岸諸国を巻き込む戦いのレシピ」。
とのツイートが紹介されていた。
「軽視してはいけない」というコメントもあったが、年間ではどういう効果になってくるのだろうか。
ちなみに以下はルービニ教授の「20年経済危機の理由」。
↓
(1)米財政刺激策の効果は2020年までに終わり、フィスカル・ドラッグが効き始める。
(2)財政刺激策のタイミングがおかしかったため、インフレによりFRB利上げが進み、ドルも上昇する。
他の経済でもインフレが上昇し、金融政策正常化に傾く。
(3)トランプ政権が仕掛ける貿易摩擦がエスカレートし、成長鈍化とインフレ上昇をもたらす。
(4)政権の他の政策もスタグフレーション圧力を及ぼし、FRBに利上げを強いる。
(5)米国以外の経済も減速する可能性が高い。
(6)欧州経済も金融引き締めや貿易摩擦等により減速する。
(7)米国を始めとして世界の資産価格は高水準。
さらに新興国と一部先進国ではレバレッジが過大になっている。
(8)一たび調整が始まると流動性不足と投げ売りが加速する。
(9)2020年の大統領選のため、トランプ大統領はイラン攻撃を強める。
これがオイル・ショックのようなスタグフレーション圧力となる。
(10)経済に問題が起こっても、金融・財政政策はすでに伸びきっており、対処の余地は大きくない。
(櫻井)
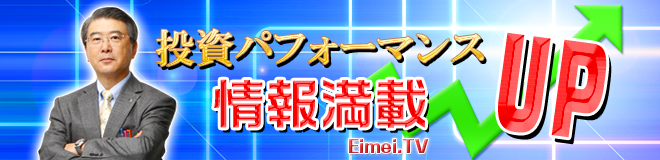








 メルマガ
メルマガ

